ケルト神話のキャラクターたち 癒しの秘術 第12回
- 鶴岡真弓
- 2025年9月5日
- 読了時間: 30分
更新日:2025年9月10日
『サー・ガウェインと緑の騎士』
——「永遠の緑/エヴァ―グリーン」の謎と真実——
鶴岡真弓
◆樹木と植物への崇敬
緑葉を繁茂させて輝く「樹木」は、世界の神話で「生命・豊饒・繁栄」の象徴とされている。
緑の「森」は「天界・異界・霊界」と同一視された。インド神話のインドラ神の庭は「ナンダナの森」と呼ばれ、仏教では釈迦が「誕生・悟り・入滅」した場所に、それぞれ「無憂樹・菩提樹・沙羅双樹 」が生えているとされる。ヒンドゥー教ではインドボダイジュの幹に女性が紐を結ぶと、女神ラクシュミーが子宝と富を授け、枝がインドセンダンの木に絡まると吉兆という。
ヨーロッパでもローマの博物学者プリニウス(23―79年)は『博物誌』で、植物には動物と同様に「アニマ(霊魂・精気・生気:ギリシャ語:プシュケ)」が宿ること、人類文明の根源では植物が「大地の賜物」として崇められていたと書いた(『博物誌』12巻I-1-5)。
強大となるローマで民衆は皇帝という現人神(あらひとがみ)を崇拝することになるが、元は「森は神々の神殿」であり「最初の神像は木」で作られ、「古来の祭式」では「高木を神に捧げ」「森に漂う静寂さ」が崇められ、人類は「樹木から最初の食物」を恵まれ、「木の皮からは衣服がつくられ」「食べ物が毎年ひとりでに得られ」たとプリニウスは記した。
人類に糧と幸福を与えてきた森や緑、木・花・実という自然の恵みへの感謝の念は、世界の神話や宗教儀礼のみならず視覚芸術にも映し出されてきた。
古代エジプトのピラミッド建築の堂々たる円柱も「樹木」の意匠から来ている。エジプトやメソポタミアなどオリエント文明で崇敬された聖樹ナツメヤシ(棕櫚)。その豊かさと美を表した「パルメット」文様が柱頭に装飾されているのが特徴である。壮大な建築の柱の大切な役割は、樹木というものが「天と地」を繋ぐ神聖な自然の垂直的な架け橋であることを歌い上げた(図❶「パルメット」文様の柱 ジョーンズ『装飾の文法』1865年)。https://echoesofegypt.peabody.yale.edu/overview/grammar-ornament-2nd-edition ❷ナツメヤシの木 Wikipedia)


19世紀後半、イギリス人のデザイナー、オーウェン・ジョーンズは、エキゾティックなオリエントの植物文様に憧れ、エジプトで調査し、その編著で今日も世界のデザイナーに参照されている『装飾の文法』(1856年)に、「太陽の光を放射するような」ナツメヤシの葉を掲載して人気を博した。
ロンドンのハイドパークで開催された世界初の万博(1851年)で、パヴィリオン・デザインの総指揮を執ったジョーンズは、彼を更に有名にするこの装飾文様の百科事典で、古代エジプトの柱頭デザインを色も鮮やかに再現したのだ。
天を衝くかのように高く伸びるナツメヤシの葉の文様は、ヨーロッパ文様史でいう「パルメット」文様の、光のごとく放射状に開く葉と、実の「デーツ」が神の恵みであることを教えている。植物・樹木はその「全身」を、人間の生命維持と幸福に捧げてくれてきた生物であり、それへの感謝を古代人はこのような美的意匠でも表したことがよくわかる。イスラム教の聖典「クアルーン」では幾度もナツメヤシを讃え、「神の与えた食物」や「神の恵みの果実」などと記されている。
一方、ヨーロッパでも樹木や植物への崇敬は、諸地域にも伝えられてきた。今述べた古代エジプトなど東方(オリエント)文明のナツメヤシ崇拝に対して、ヨーロッパの西方(オクシデント)では、ジョーンズの足元のイギリス(ブリテン)諸島に、オリエントの巨大なナツメヤシに勝るとも劣らない、大樹にもなる緑の樹木が神話や歴史の中で語り継がれてきた。
その植物・樹木とは「ケルト文化」で崇敬され物語られてきた「樫の木」である(図❸ 樫の葉と実 ❹樫の木立とドルイド、鎌、ヤドリギ、ストーンヘンジ」 出典:フランシス・グロース『イングランドとウェールズの古代遺物』1773-87 年より)。


英語で「オーク」と呼ばれ日本語では「ミズナラ」とも呼ばれるナラ科のこの樹木は、常緑と落葉の種類があるが常に緑葉を絶やさない樹木として縄文時代の日本列島でも大切に用いられた。最大級の縄文集落、青森県の三内丸山遺跡などからも出土している。近現代文学ではアイルランドの詩人イェイツなどのケルト文芸文化復興によってケルト神話や伝説が英語で再話され世界に知られるようになると、文学的に「樫の木」という名が定着し広まった。
とりわけこの木は古代ケルトの神官・予言者・詩人である「ドルイド」の聖樹として伝えられてきた。「ドルイド」と「樫の木」の結びつきはガリアやブリタニアのケルトの言語文化集団(ケルト文化の人々)を征服する古代ローマ人による古典資料に「史実」として印象的に伝えられている。ローマの博物学者プリニウスが『博物誌』で詳しく伝えたように、オークの木・樫の木はドルイドの儀礼で聖樹とされ、それに宿る「ヤドリギ/パナケア」も神聖な治癒の木として崇められた。最初の月の6日目に黄金の鎌でヤドリギを切り落とし、白い布で受けて、それを万能薬(「パナ=すべて」+「ケア=治癒」)としたという。オークの木は人の身心に「癒(ゆ)」をもたらすものを宿すと考えられた(プリニウス 大槻真一郎編『プリニウス博物誌 植物篇』新装版 八坂書房 2009年)。
このような信仰が背景にあったことに思いを馳せるとき、緑葉の樹木とその森の神秘が、ヨーロッパのなかでもケルトの神話や歴史に伝わり物語られてきたことにも納得がいくだろう。
まず以下で、深き「緑」の意味を主題化した、騎士ガウェインの体験する神秘の森と城での出来事を読み、ケルト神話の森に歩み入ってみよう。
◆『サー・ガウェインと緑の騎士』——首取りゲームの意味
ケルトの言語文化の人々の緑の樹木・森・植物信仰を深く示唆する神話の筆頭にあるのが『サー・ガウェインと緑の騎士』である。
アーサー王物語の一つである『サー・ガウェインと緑の騎士』は、作者不詳の中英語頭韻詩で綴られた14世紀後半の写本によって伝わっている。現代では本書冒頭にも登場したJ・J・Rトールキンも、準創造を含む現代語訳を手がけたことで知られている(J・J・Rトールキン『サー・ガウェインと緑の騎士——トールキンのアーサー王物語』山本史郎訳 原書房 2019年)。
物語は、突然の見知らぬ異形の騎士の登場から始まる。
時はクリスマス。アーサー王のキャメロット城の大広間に、異様にも全身緑色のいでたちの騎士が突然現れる。騎乗の馬も緑。手には「斧」と、常緑の「柊(ひいらぎ)」。なんとこの見知らぬ騎士が申し出たのが、「首斬りゲーム」であった。「斧」は「死」をもたらすもの。「柊」は永遠の緑、「生・命」を示唆している。
「今ここで吾輩の首を刎ねる騎士は、おらぬか。斬ってみよ。ただし一年と一日後に、同様の首伐りの反撃を、吾輩から受けるのだぞ」と、挑発した(図❺ 『サー・ガウェインと緑の騎士』写本 14 世紀末 イギリス ウェスト・ミッドランド地方 大英図書館蔵)。

受けて立ったのは、まだ円卓の騎士ではなかった若きアーサーの甥ガウェイン卿だった。
ガウェインは、ひと思いに「緑の騎士」の首を刎ねてみせた。しかし騎士は何事もなかったかのように、己の首を拾い、「来年はおまえが、首斬りのお返しを受けよ」とガウェインに約束させる。
さて1年と1日後、ガウェインは、「緑の騎士」が言い残した「緑の礼拝堂」を目指して旅し苦労の末に、ある立派な城に辿り着いた。ガウェインは客人として城主と美しい妻に歓迎された。首斬りの仕返しをする礼拝堂は2マイルほど先にあり、当日までは城で休むようといわれ、それに従うことにした。
加えて領主は毎日狩りに出かけるので、吾輩の「獲物」は何でも与える、その交換条件としてガウェインもその日にこの城の中で獲得したものを城主に与えるという約束も交わした。
城主が狩りに出かけると、奥方がガウェインの寝室を訪れ誘惑した。が、彼は禁欲し一度のキスしか許さなかった。城主が戻り、仕留めた「鹿」をガウェインに渡し、ガウェインは城主に「1つのみのキス」を返した。が、キスの出所は明かさなかった。
翌日も奥方はガウェインを誘惑したが彼は再び丁重に誘いを断り、同じように狩りで獲った城主の「猪」と「二度のキス」を交換したのみであった。
三日目の朝に彼女はもう一度やってきて、誘いをガウェインに断られると、記念に金の指輪を差し出し、それもガウェインが断ると、奥方はせめて私の体に巻いているこの「緑と金の絹の帯」を受け取ってほしいと懇願した。
実はこの「緑の帯」には魔法がかかっており、どんな危害からも身を守ってくれるのだという。ガウェインは戸惑ったが、翌日にはあの約束の首斬りゲームの仕返しを受けることから、身の保全を思い、「緑の帯」を受け取り、二人は3つのキスを交わした。ただし奥方はガウェインにこの「緑の帯」の贈物を夫には秘密にすることを誓わせる。
夜、城主は獲物の「狐」を持って戻り、3つのキスと引き換えに、獲物をガウェインに与えたが、ガウェインは帯のことは黙っていた。
遂に翌日、ガウェインは腰に「緑の帯」を巻いて、「緑の礼拝堂」の外の洞窟のある土塁のような場所で「緑の騎士」が斧を研いでいるのを見つけると、約束通りガウェインは首を差し出した。すると城主は斧を何度かガウェインの首の手前で寸止めした。怒ったガウェインは一撃するように告げ、遂に 「緑の騎士」は斧を振り落とした。しかしガウェインの首は、かすり傷を負ったのみでゲームは終了した。
「緑の騎士」は、自分は魔法で変身した城主ベルティラック・ド・オーデゼールであること。この冒険のすべては、ガウェインが城で見かけた、見知らぬ「老婦人」の策略であること。その老婦人はアーサー王の異父姉の妖精モルガン・ル・フェ——つまりはガウェインの叔母であることを明かした。
モルガン・ル・フェはその魔術と妖力で、アーサー王の騎士たちを試したり、王妃グィネヴィアをも怖がらせていたのである。
城主はガウェインが3度目の打撃で負ったかすり傷は、ガウェインが奥方からの「緑の帯」の贈物について城主に話さなかったためであると明かした。ガウェインはこのことに恥じたが、「緑の騎士」は咎めず、二人は友好的な仲のまま別れた。
ガウェイン自身は約束を守れなかった戒めとして、自ら「緑の帯」を着けてキャメロットに戻った。アーサー王の円卓の騎士たちは、彼の勇気と礼節を讃えた。「緑の帯」は、むしろガウェインが騎士道の模範を貫いた徴となった。
◆緑の森の城の「緑の騎士」「緑の礼拝堂」「緑の帯」のメタファー
『サー・ガウェインと緑の騎士』の神話において、アーサー王の大広間に突然「緑の騎士」が現れたのは「クリスマス」の季節であった。それは自然界の生命が寒さに震え、灰色の世界に変わる厳冬だが、その季節にも永遠の生命循環を営むエヴァーグリーンの世界が存在するということを示している。ケルトやゲルマンの人々は北ヨーロッパの民であり、この物語が設定された「クリスマス」は、北半球で最も太陽の光が弱まる「冬至」の日を、キリスト教が吸収した祭日である。冬至には最も深い闇が地上を包む。しかし冬至を超えれば翌朝には一陽来復の陽光が地上に再びもたらされる祭日である。現実にはまだ厳冬は続き、大地には穀物も家畜も生命が育たないが、樅(にれ)や柊はエヴァーグリーンの葉を繁茂させて光のように輝いている。
『サー・ガウェインと緑の騎士』の物語は、突然現れた騎士の手に「斧」を持たせ、もう一方の手に「柊」の緑の一枝を持たせて登場させる。既述したように「斧」は生きとし生けるものへの「死」を表象させるが、緑滴る「柊」の枝は永遠の「生命循環」=「生」を表象していると解釈できるだろう。つまり同時に「斧」は冬至で最も深くなる「闇」を表すが、そこから蘇る「柊(の緑)」は「光」を表象しているだろう。
さらに読み込めば、この世にある「人間界」は「有限の生命」の世界であるが、「自然界」は「無限の生命」の世界であるということであるだろう。
すなわち『サー・ガウェインと緑の騎士』の神話は次のことを知らせている。
「森は異界である」。緑の森は、人間が自然を征服しコントロールできる領域ではないこと。そこには人間が及べない「生命力」が満ち溢れ、常に「生命循環」がおこなわれている聖域であること。「緑の森」には計り知れない、畏怖すべき、生命力が秘められ、そこに真の「富」が埋蔵されている。城主が緑の森に狩りに行き獲得する「鹿」「猪」は聖獣であり、肉も皮も角も人間に供され恵みと富となる。
しかし人間(ガウェイン)は豊饒の「森の全てを狩って(刈って)はならない」。人間は「自然界」からの恵みに対して、常に(森が枯渇しないように)返礼をしなければならない。ゆえに3日間、城主の獲物(自然界の恵み)に対してガウェインは城で(奥方から)得たキスを毎日城主に「お返し」した。
また森は異界であるのだから、城のある「森はこの世とあの世の境界」である。1年前の約束を守りガウェインは正に命(首)を賭けてこの「生と死の境界」にやってきた。いかにもガウェインはその「首=生命」を斬られに来た。
すなわちこの神話の主題は「首」である。神話の冒頭で「緑の騎士」の「首」は斬られても「生きていた」のは、「緑の騎士」はエヴァーグリーンの「生命循環」のゾーンである「緑の森」の表象であり、不死であるからである。一方、人間(ガウェインの「首」)は不死ではなく、それは究極の「死」を象徴する。
この神話において「緑の騎士」や奥方の「緑の帯」の「緑」は、「生」を保証すると同時に、それをないがしろにすれば「死」がもたらさせることを人間(ガウェイン)に警告している。「緑」とは、不死=エヴァーグリーンであるゆえに、人間の「生」を護り育てる。すなわちウェインの受けた「城での宴の歓待」「奥方の旺盛なエロス/接吻」「<緑の帯>が騎士の身を護る効力」を表象する。と同時に、それを受け入れなければ(約束を守らなければ)、森は人間を救済しないことを告げているだろう。(ガウェインは、自然=「緑の騎士」に対して非礼をはたらいたとすれば立派な騎士にはなれない。)
ではなぜこの物語は「斬られる首」をモチーフしたのだろうか。
戦士や騎士の栄誉を称える「斬首競技(首斬りゲーム)」のテーマは、戦士や騎士が優れた勇者たることを物語る神話や伝説が知られてきた。ヨーロッパの神話伝説でこのテーマの最も古い物語は、8世紀の『ブリクリウの饗宴』で、緑の騎士のようにクー・フーリンの敵の首を斧で3回寸止めして、怪我をさせずに立ち去らせる点でガウェインの話と似ている。また斬首のやり取りは、12世紀後半の『カラドックの生涯』(クレティアン・ド・トロワ『ペルスヴァル、聖杯物語』の匿名の第一続編に組み込まれた中期フランス語の物語)にもみられる。この物語は騎士の名誉を試すために斬首ゲームがおこなわれたことを示している。
13世紀初期の『ペルルヴォー』では、ランスロットに斬首の挑戦が与えられ、その中で騎士は彼に自分の首を切るか、さもなければ1年後に同じ場所へ来て同じ危険に身を晒すことに同意した。ランスロットが到着すると、町の人々は祝杯を挙げ、ついに真の騎士を見つけたと絶賛する。
ガウェインと緑の騎士の物語は、ガウェインの物語に、島のケルト語文化圏の神話の宝庫、中世ウェールズの物語集『マビノギ』の第一話が提供している可能性もある。『マビノギ』ではダヴェッドの領主が、異界(アンヌン)の領主アラウンとお互いの役割を、1年間入れ替わった。しかしプイスはこの間アラウンの妻と関係をもたず、二人の領主の間には永続的な友情が築かれた。奥方の誘惑テストの要素のみならず、挑戦または交換の決着が完了するまでに1年が経過するのも『サー・ガウェインと緑の騎士』に共通している。
そしてここで重要なのは、プイスやガウェインを試す脅威の相手の騎士や領主が「異界から」やってきたことである。
緑の森は、単にこの地上の自然界の場所を示しているのではなく、城と礼拝堂を囲む緑(の森)は、謎めく神秘の「異界」に繋がっている時空であるということを伝えている。「緑の騎士」の顔・身体全体が「緑の森」であり、植物も動物も光も水もここに集まってくる(図❻ 「緑の騎士」 https://villains.fandom.com/wiki/Green_Knight?file=Sirgawain.jpg)。

では「斬られる首」は、「緑の騎士」の背景にある緑の森、緑とどのように意味づけられているのだろうか。
◆「斬られ再生する緑の首」——「グリーンマン/緑葉の人間」の謎
「緑の騎士」はアーサー王の城の広間で堂々と自らの「首」を再生させた。ガウェインも覚悟のもとに約束を守り、首を斬られる覚悟で臨んだが、「緑の騎士」の計らいで首はかすり傷に留まり、一命を取り留め、文字通り首が繋がった。
常緑の自然は幾度でも再生することを、「緑の騎士」が己の「首」の即座の再生で証明してみせた。言い換えれば、常緑の自然界は、「死からの再生」を永劫に繰り返しているということを示したといえるのだろう。
現代に伝わる『サー・ガウェインと緑の騎士』の写本は14世紀のものであり、中世キリスト教の時代の様式でいえばゴシック時代に当たる。そのゴシックの大聖堂や教会にも、不思議な「緑の首=頭部」の像が蔓延(はびこ)っていたことを読者はご存じだろうか。それは今日「グリーンマン」と呼ばれるものである。実際の聖堂の浮彫のほか、13世紀に生きたフランスの芸術家ヴィラ―ル・ドゥ・オヌクール(生没年不詳)の丹念なスケッチ・ブックによって、当時のヨーロッパの聖堂でいかに「グリーンマン」の表現が盛んにおこなわれていたかがわかる。中世で最古の現存する文献、通称『画帖(アルバム、スケッチブック)』の作者で、そのスケッチ・ブックはゴシック建築の細部の装飾までを描写しており、「グリーンマン」についても生き生きと描いている(図❼「グリーンマン」 ヴィラール・ド・オヌクール『画帖』 13世紀 フランス国立図書館蔵)。

「グリーンマン」の特徴は、①顔全体が緑葉で表され、②主に口から葉を吐き出し、③顔のすべての開口部(目鼻口耳など)から緑が萌出(もえいで)ていることである。民間の「常緑」や「樹木」への崇敬との関連が指摘されている(『グリーンマン』)。ここに示したドイツ、バンベルク大聖堂の作例はとても有名である(図❽ 正面・騎士像の足下・横顔)。
❽
明確な起源はわかっていない。ギリシャ・ローマ神話のディオニュソスやバッコス、ローマ神話の森の神霊のシルウァヌスなどの像からの影響も考えられるだろうし、キリスト教にとっては「神の被造物」に入れられる。しかしいずれにしても「グリーンマン」の始原には、北方ヨーロッパの異教の民間信仰の「異教の精霊」の特質がある。祟(たた)りがなきように聖堂内に納めたなどとも推測されているゆえんである。
バンベルクの大聖堂で、騎乗の騎士に「踏まれている」構成・図像は、仏教美術の図像において、仏像が踏んでいる邪鬼を喚起させるかもしれない。異教に対するキリスト教の勝利、正義による邪の制圧、文明による野蛮の駆逐……などの図にも見えなくもない。
しかし「グリーンマン」は、聖堂内の視野において、忌避されるどころか、教会の門、天井の要石、柱頭、コーベル、聖務共唱席などきわめて様々な場所に表され、むしろ聖堂を護る、キリスト教化された精霊のような様相を呈している。このバンベルクの作例の相貌もむしろ王のように堂々としている(ウィリアム・アンダーソン『グリーンマン―ヨーロッパ史を生きぬいた森のシンボル』板倉克子訳 河出書房新社 1998年)。
ここで私見であるが、上記に解釈してきた『サー・ガウェインと緑の騎士』の物語の動機と結末を結ぶ、「斬られる首(頭部)の再生」のテーマが、「緑の人間(男)」の「首・頭部」にも共有されていると考えられないだろうか。もちろん『サー・ガウェインと緑の騎士』の「緑の騎士」そのものが「グリーンマン」であるという意味ではなく、「緑の森」、「常緑」、自然の「生命循環」が、「斬られる首の再生」に異教の記憶として投影されているのではないだろうかという意である。
(「緑の騎士」の)「斬られた首」は「再生」する。それは「緑」の大自然の再生と「生命循環」そのもののメタファーであるという推論である。
『サー・ガウェインと緑の騎士』における「緑の騎士」の首と、「ガウェイン」の首は、「異界」と「現世」の差異を見せつけている。生死の運命においてコントラストを成し、かつ照応していた。その物語において「斬られる首」は、異界の森の「緑の騎士」と、現世の騎士のガウェインのそれぞれを意味付け、「(自然界という)異界と(人間界という)現世」の境界に置かれ、両者の関係を対比的に結びつけている。「斬られる首」は、「異界と現世」を(交流的に)結びつけるのではなく、「生と死」のコントラストを(同時に)表象する
すなわち「妖精=緑の騎士」の首は、斬られても常に再生する「自然界の生命循環」を顕す。一方、1年後にガウェインが斬られに出かけた「人間=ガウェイン」の首は「人間界の限りある生命」を表象している。
そして中世キリスト教の聖堂に「グリーンマン」という「緑葉の首(頭部)」という造形が、数多く刻まれた理由は、それがキリスト教の聖堂内を飾ることにおいて、キリスト教信仰に寄与すべく取り込まれたと考えられるのである。それは異教の緑の精霊の祟りを鎮めるためであるというより、より積極的に「キリスト教信仰の文脈」すなわち「イエス・キリストの死からの再生」という「生命循環信仰」において飾られたと考えられないだろうか。
◆「死からの再生」としての樹木
中世キリスト教美術の写本や壁画やレリーフの「磔刑のキリスト」像の十字架には、しばしば「緑葉」が表現されたことが思い出されよう(図❾ 「磔刑のキリスト」の樫の葉 ヴィラール・ド・オヌクール『画帖』)。

1260 年にジェノヴァ司教ヤコブス・デ・ヴォラジーネによって書かれた聖人伝『黄金伝説』によれば、亡くなったアダムの口に、息子のセツ(セト:カインとアベルの弟)が、天使がくれた種を撒くと、そこから樹木が生え、回りまわって、それはイエス・キリストの磔刑に使われる材木となったといわれるが、その材木=樹木の十字架に架けられたキリストは、三日後に蘇る。
このように前述の中世フランスの芸術家オヌクールが、十字架に「葉」を描いているのは、キリストの復活の予兆としての緑葉を添えたからであるが、よく見るとこの葉は、地中海地方の文明ではブドウ唐草などを描くところを、キリスト教図像には則らない葉を描いていることに気づかされるであろう。
その「葉」(植物)はなにかといえば——「グリーンマン」(前掲:図❼)バンベルクの聖堂の古典的なステイタスを匂わせるアカンサス(和名:葉あざみ=ハアザミ)の葉でなく、しっかりと北方ヨーロッパの自然を映し出してワイルドに開く「樫の葉」を表現していることに注目しなければならない。それは「柏の葉」とも呼ばれ、我が国では端午の節句の餅を包む、たおやかにカーヴする切れ目のある青葉である。
ここで葉は素朴に生き生きと、なにより画家自身にとって親和的で身近な植物として描かれている。ヴィラ―ル・ドゥ・オヌクールはフランス人であり、フランスはかつてのガリアの地であった。彼の祖先や同時代の民衆が親しんでいる、実際に見られる植物・葉は(いうまでもなくギリシャ・ローマ建築を飾ってきたアカンサスではなく)「樫の木」の葉でなければならなかった。
オヌクールが同じ『画帖』に描いていた前出の「グリーンマン」の「葉」の繁茂の表現の力強さ。その勢い、豊穣性が、この磔刑の十字架の葉にも同じく生命は「死から再生する」波動をもって表現されている。ヴィラ―ル・ドゥ・オヌクールが同じ『画帖』において示した「グリーンマン」の「葉」の繁茂と同じ力強さ、勢い、豊穣性において、この磔刑の樫の葉は、同じ波動をもって描かれている。おそらく13世紀のオヌクールの時代にも、フランスやスイスやベルギーでも、古代ガリア時代にまで遡る聖樹「樫の木」への信仰は記憶され生きていた。これはキリスト教図像が、民間に生きていた植物・樫の木信仰が結びついた貴重な画といえるのではないか。
◆「樫の木の森」の恐ろしさと畏敬
遡ると、ケルト文化において「樫の木の森」はガリアにもイスパニアにもヒベルニア(アイルランド)にも、遠くケルトの一派ガラティア人のいたトルコにもあった特別の森だった。古代ケルト社会にとって「樫の木の森」じたいが「聖域」であった。
この信仰の史実は古代ガリア語由来の「ネメトン/聖森・聖所」という呼称に残っている。実際、地名としてスコットランド(「メディオメネトン=中心の聖森」)や、ケルトの一派ガラティア人がいたトルコやスペインには(「ドルネメトン」=樫の木の聖森)などが伝わっている。「ネメトン」は「聖所・聖域」も意味したので、キリスト教以降の中世ケルト語文化圏のブルターニュ南西部のベネディクト派 修道院のあったロクロナンではネメトンとして伝えられる森に囲まれていた。
ケルトの人々の居住地だった現フランスの古代ガリアのみならず、ブリタニアに残るラテン語の碑文には、ネメトンを神格化した女神「ネメトナ」の名が刻まれているものがある。この女神はおそらくケルトと接していたゲルマンの人々が崇拝した「ネメテス」と語源的に関係している。ガリアを属州としたローマ人貴族も青銅板(マインツ近傍出土)に刻んで崇拝した。なおガロ=ローマ社会で崇拝された女神ネメトナが軍神マルスとペアとされる概念は、アイルランド神話の戦いの女神「ネヴァン」に関係するかもしれない。(図❿ドイツ南西部 ライン川 女神ネメトナの聖域 碑文出土地:wikipedia)。

ケルトの聖森への崇敬とその受難は、神話や伝説や歴史において語られ、その痕跡を今日まで示している。
紀元前1世紀、「ネメトン」を、邪教の聖域とみなし敵視した、ガリアの征服者カエサルは、ケルトの聖森を焼き払った(後述)。しかしさらにそれは生き延びた。
ローマ帝国は、自然を開発して人間が構築する都市を築いた。だが、その陰で、属州となったガリアには巡礼が通う聖なる水辺が、セーヌ川の源流やシャマリエールの泉の聖所にあり、そこに樹木から伐り出した木材を用いて、病気治癒のための病人の身体の部位を象り、それを聖なる水に投じて祈るという慣習が生きていた。そしてその水辺は、樫の木や白樺や柳やハシバミの木が揺れる聖域だったのである。
また聖樹・樫の木の実であるドングリを食べる「猪」はケルト神話に頻出する獣の筆頭で、「異界」の動物であり、その猛進によって英雄の冒険や運命に関係している。ウェールズの神話「キルッフとオルウェン」ではキルッフがアーサー王とその騎士たちに助けられオルウェンを嫁として迎えることができた。が、彼はそのそもそも母が産気づいたのは「豚(家畜化された猪)」の囲いの所であった。また嫁に迎えることができたオルウェンの父は巨人で、嫁取りのための最大の難題を巨人がオルウェンに課すのだが、それは「猪が耳の間に挟んで持っている櫛とハサミ」を奪って来るようにというものであった。それはその猪も、謎めいた異界に棲むものであった(別稿参照のこと)。
このケルトの「神話的聖獣」である猪・豚の繁殖力は、厳冬を生き抜く北ヨーロッパ人に最高のビタミン源となった。ゆえに古代ケルトでは「猪の神」がガロ=ローマ時代の「神像」としても表現された。この像は頭部と身体は人間の形をしているが、胴体に「猪・豚」が刻まれているのがわかるだろう。ガリアではこの神は「モックス」と呼ばれ、豊饒や生命力が祈願された(図⓫「猪の神 モックス」 胴体に猪の像 フランス デュフィニエ出土 フランス国立考古学博物館蔵)。
この猪・豚の餌こそは樫の実であり、15世紀フランスの有名な写本の「月次絵」にも描かれている。北ヨーロッパではケルトの異教時代から厳冬に入る「11月」に、森で猪・豚にドングリを食べさせ肥やす。その中から万霊節(ハロウィンの起源のケルトの大晦日で、冬のはじまりの祭日)までに、越冬するもの以外を屠り、それからの「闇の半年」を生き抜くための最も大切な食糧とするのである(図⓬ 『ベリー公のいとも豪華なる時禱書』15世紀 「11月・森でドングリを猪に与える月 シャンティイ美術館蔵)。
⓫ ⓬
その餌・滋養は「樫の木」から恵まれる。常緑と落葉の種類があるが緑葉を絶やさず、大木になる偉容をみせる。その実が、生命を支える食物であり、よってこの木そのものは、再生を繰り返す生命と富の象徴とされたのである。
◆「聖森=ネメトン」を破壊したローマ軍
したがってケルトの森の聖所である「ネメトン」は樫の木の聖域であった。
ガリアに侵攻したローマは、その聖域を潰そうとした。むろん古代ローマ人にも樹木崇拝はあった。ローマの神話的祭壇には森を守護する神シルウァヌス(森と未開の地の守護神、畑の境界と牛の守護神、狼から家畜を守る神)が祀られ、大カトーの『農業論』では家畜の安全を守ってくれるようマルス・シルウァヌス (Mars Silvanus) に供物を捧げている。
しかし共和制ローマから帝国となっていくローマの膨張は「自然界」を征服し大理石の都市を建設し「人間界」を拡大して、異文化の地域を次々に属州にしていった。ユリウス・カエサルにとって、自然の森は「邪」の棲む場所として打ち倒すべきものとなった。
カエサルはアルプス以北に乗り込み、紀元前58年から51年にわたりガリア(現フランス、スイス、ベルギー地方)への征服戦争に乗り出した。人間の世界、ローマの権力の絶頂にいた将軍カエサルにとって、ケルトの森の聖域は、おぞましい蛇が木々に絡みつく「異教」の森のほかの何ものでもなかった。
約2000年前、カエサルは南フランス、現プロヴァンス地方のガリアの森(遺跡:アントルモンなどがある)を焼き払うに至る。
ガリアのネメトンを恐れてか、ガリアを征服したカエサルが破壊したことと、「ガリアの森のイメージのおぞましさ」を、後世の詩人ルカヌス(以下の資料ではルーカーヌス)が『ファルサリア 内乱』に記している。ガリアの森は人身供犠の場で、泉、木偶、音をたてる穴があり、火によらずして輝き、根元に蛇が絡みつくと詠じたのである(ルーカーヌス『内乱 パルサリア』上 大西英文訳 岩波文庫 2012年 第3巻414-470 pp.144-148)。
ケルトの聖域の森の焼き払いは、イタリア半島と地続きのケルト文化圏のガリアだけでなく、島のブリタニア(ブリテン島、イギリス本島)でもおこなわれた。紀元後77年、ローマ人はウェールズのアングルシー島のドルイドの森を破壊した(図⓭ 「ドルイドの殺戮」1836年 イギリスの版画)。

ローマはブリテン島を属州として、紀元後43年から400年代まで、ケルト諸語の人々を支配下に置いた(ローマン・ブリテン時代)。ローマ軍は、ブリテン島の西に突き出たウェールズのアングルシー島の樫の木の森を焼き払い、大勢のドルイドを殺害したことは今日まで伝えられている。
樫の木の森が焼き払われることは、ケルト文化の人々によって、自らの身を焼かれるに等しいことだった。
ここで思い出されるのは『サー・ガウェインと緑の騎士』の神話の城も「樫の森」に囲まれていたことである。
この物語のゆかりの場所、ロケーションについて様々な推測がなされている中で、実はガウェインの「緑の礼拝堂」への旅に関して、上述のドイルドの聖森のあったウェールズの「アングルシー島」がガウェインの詩で言及されている。詩の700行目、ガウェインが通過するのが、「アングルシー島のホーリー・ヘッド(「聖なる頭」)」である。なおこの地名の「聖なる頭」が、斬首された聖人の頭に関係する地名だとすれば、7世紀ウェールズの 処女殉教者の聖女ウィニフレッドが受けた斬首と関連があるのかもしれないという。彼女の叔父の聖人が、頭(首)の傷を癒し白い傷跡だけを残して取り戻したと伝承される。ドルイドの緑の聖森のあったウェールズの地域は『サー・ガウェインと緑の騎士』の旅の舞台となった可能性も高い。
古代や中世において北ヨーロッパ人が崇めた邪教の木として「オークの木を伐り倒す」事件は、後の中世ドイツでも起こった。723年ドイツへの最初のキリスト教伝道師であった、イングランド人聖ボニファティウスが、ゲルマン系の人々も崇めていたこの木を斧で切り倒したことはよく知られている。キリスト教史の側からみれば、これはボニファティウスの勇気ある快挙であった(図⓮ 「ヘッセン州で樫の木を切り倒すボニファティウス」ベルンハルト・ロード版画 1781年)。

自文化とは異なる異教で崇拝されている木は、邪教のシンボルとして伐り倒さねばならないと考えられていた。古代ローマ人や、中世キリスト教からみると「ケルト」の文化伝統は、ヨーロッパの文化史の中で恐れられ差別もされてきたが、しかしそのことはケルトの文化や神話や芸術が、この世の現実の理路では説明できない神秘の側面を表現していると認識されてきたことを示している。
実は聖ボニファティウスによる「樫の木の打ち倒し」は、そのキリスト教的な信念による、異教の木の伐採という快挙でこのエピソードは終わったのでは「なかった」。
聖ボニファティウスが樫の木を打ち倒すと、逆説的だが、その後ろに樅(モミ)の木が生えてきたという。神の子の降誕を祝うクリスマスは、北方ヨーロッパの人々にとって「冬至」に重なる、太陽の蘇りの祝日に続いて訪れる。クリスマス・ツリーは、樅や松や唐檜(トウヒ)など「常緑針葉樹」が、神の子の誕生を祝うクリスマス・ツリーとなっていった。クリスマス・ツリーを飾る慣習は、したがってイタリアを含む南の地中海地方ではなく、ルネサンス期のドイツやエストニアのルーテル教会で発展した。キリスト教カトリックの本山ローマを戴くイタリアで広まるのは19世紀末で、欧米の家庭で飾られるようになったのが近代からである。
北方の厳しい霧と森の大地で、緑の伝説はより深い神話と伝承を編み上げた。2500年以上の時空を超えてヨーロッパのケルト文化に、特徴的な樹木崇拝が生き残ったのもその自然環境と結びついている。
ヨーロッパの自然崇拝、樹木・植物信仰は、神話伝説とともに造形美術が力強く伝えてきたゆえんである。
◆フランス、古代ガリアのエンブレムとしての「樫」
その「樫の木」崇拝に戻ると、挙げておかねばならない近現代に蘇ったそのヴィジュアルな証拠がある。
今日においてオヌクールの祖国フランスの歴史的な「国章」は「樫の木」であることは偶然ではない(図⓯ フランスの「国章」 樫と月桂樹 ⓰パリ市の紋章 樫と月桂樹)。
⓯ ⓰
青地に、樫と月桂樹の2本の枝の上に、薄紫色の護衛(リクトル)の束帯が十字に交差し、リボンが巻かれ、その上に黒字で「自由、平等、友愛」という標語が刻まれている。「国章」として制定されたのは20世紀初頭であるが、「樫の葉」はフランスにとって重要なシンボルである。ヨーロッパ文明の古典といわれてきたギリシャ・ローマの特にギリシャを表象する月桂樹だけでは、アイデンティティを示せないという意思が「樫の葉」の国章には滲み出ている。
フランスは「ヨーロッパ」の基礎をつくったシャルルマーニュ大帝の戴冠(800年)以来、様々な「古典」文化を吸収し、ナポレオン1世の肖像画にあるように桂冠の「月桂樹」によって地中海文明(ギリシャ・ローマ)のクラシックの要素を吸収した文化国家である。が、フランスが歴史の根源に遡るとき、かつてケルトの言語文化をヨーロッパ大陸の中央で担った「ガリア」であったフランスが、このようなエンブレムで明瞭に表されていることを、見逃してはならないのである。
したがってフランスの首都パリ市の紋章も「樫と月桂樹(の枝葉)」であることは驚くに当たらない(図⓰パリ市の紋章 樫と月桂樹)。
フランスの国とその首都は、己のアイデンティティを、古代ローマでもなく、古代フランク(ゲルマン)でもなく、古代ローマより古いアルプス以北のガリア(ケルティカ)文化の根源にある植物・樹木・緑への畏敬を、古典的な地中海文明の「月桂樹」に敬意を払いつつ、北方のケルト文明の「樫」によって深くと表象している。
◆現代へ:ケルトの樹木の祭日「ベルティネ」と「メイポール」
ヨーロッパの「ケルトの4つの季節祭」の中で、夏の到来を寿ぐのがメイデーの起源の「ベルティネ祭り」であり、この祭りの文字通り中心には「五月の木」が立てられ、ケルト起源の樹木崇拝が再現される(図⓱)。

「ケルト暦」の4つの季節祭は、「冬/死➡春/再生➡夏/成長➡秋/収穫」と循環する。農耕牧畜の生命循環を刻む。ケルトの暦は、約2000年前のケルト語文化圏であったガリア(現フランス)から出土したガロ=ローマ文化の青銅板に伝えられている。1年のサイクルは、後の島のケルトでいう大晦日10月31日(万霊節/サウィン:キリスト教ではハロウィン)が重要な1年の締めくくりであり、死者があの世から1年に一度この世に回帰する。この夜から飢餓も覚悟せねばならない「闇の半年」が始まる。
しかし、その半年を無事生き伸びれば、「夏」が到来し、人々は「5月1日/ベルティネ祭」に、広場や戸口に「五月の木」を立てて夏の到来を祝う。
その木は特別に前日に森から伐り出す。フレイザーは「アイルランド人は「五月一日に緑の樹の小枝を家に結び付けておくと、その夏は[家畜]の乳がふんだんに出ると信じている」という」と記した(フレイザー『金枝篇』永橋卓介訳 岩波文庫 全5巻1952年 のち改版 p.257)。この木こそメイデー(五月祭)の聖なる木「メイポール(五月の柱)」の起源だった。人々は現代でも天辺からリボンを下げて飾り、家畜や穀物の成長を祈って踊るのである。
イングランドでは18世紀後半に「緑のジャック(ジャック・イン・ザ・グリーン、ジャック・オー・ザ・グリーン)」が祭りに繰り出すようになった。全身が緑のこのキャラクターは、樽やワイヤーに緑葉や花を巻き付け、人間がその中に入り練り歩く。「木の中の人間(マン・イン・ザ・トゥリー)」の仮装をする地方もある(図⓲)。

こうして、本書で紹介したケルトの神話伝説の『サー・ガウェインと緑の騎士』物語の主人公は、今日もヨーロッパ各地に伝わる「樹木崇拝」の祭礼に現れるこれらの「緑の人間=グリーンマン」に映し出されている。
この緑の人間は、神話的存在だが、人間の切実な、「生命循環」への祈りを背負っている。
『サー・ガウェインと緑の騎士』での「緑の騎士」が体現した「斬られる首」のゲームは、騎士道の修練を超えた、自然の永遠の緑を人間が絶やさぬことを、ガウェインに約束させた物語でもある。
人間が守るべき「緑(大自然)の首(生命)」は、人間の心の首にかかっている。
「緑の騎士」は「緑の森」の化身として、大自然のエヴェーグリーンの生命を「首(=生命)」というメタファーで示すことによって、「人間と自然」とのあいだの交流と緊張関係を伝えようとしている。
我々近現代人がすっかり忘れ去った、「自然を侵さない」という倫理を繰り返し思い出させる神話である。と同時に、「緑の領域」においては、人知の及べない、より深い力、驚異が、モルガンの魔術のように、うごめいていることを知らせている。
「緑の騎士」は人間の世の生命の有限性を、人間に思い出させ、大自然の生命への畏敬を忘れることがないよう、「緑の騎士」は自らの首、すなわち大自然の生命そのもののメタファーとしての「首」は、斬られても「再生すること」、永遠に「生命循環」を営んでいくことを示した。いいかえれば「死からこそ生が再生する」奇跡である。
この真理を人間(ガウェイン)に深く伝えるために、緑の森の城の「緑の騎士」「緑の礼拝堂」「緑の帯」をモルガン・ル・フェは妖計によって創造し、ガウェインに試練の経験を与えた。
それはこの世、現世では身に着けることのできない修練であった。
「この世=人間界」と「異界=自然界」の交流は「境界」で起こる。ガウェインが赴いた「緑の騎士」の城や、首を差し出した「緑の礼拝堂」がその境界であった。ガウェインのようにそこに至り経験し学んだ者だけは、何かを得て人間界への帰還できるという訓えを、この神話は孕み人間を力づける。
同時に「自然」は神々の領域であり、ゆえに人間にとってそこは、人間が学び鍛えられる永遠の修験の道に通じていることを訓えている。













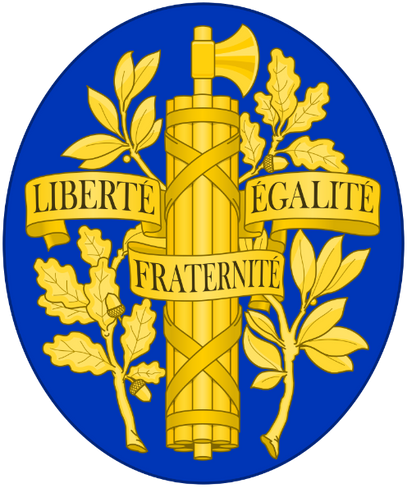


コメント